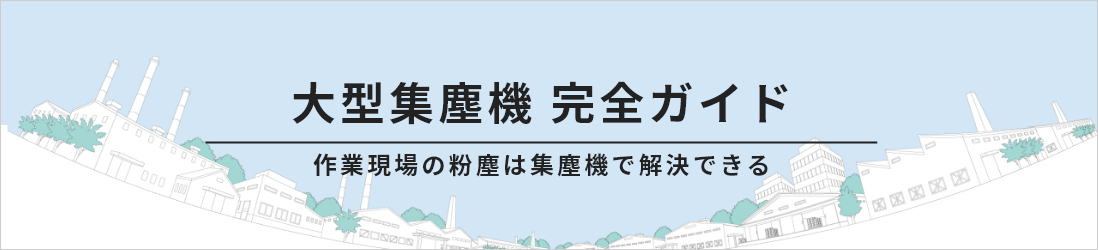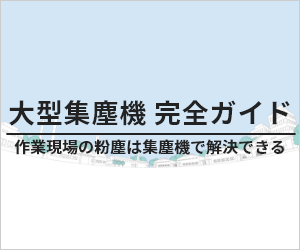集中集塵は工場全体の粉塵を一箇所で処理し、効率的なメンテナンスとエネルギーコストの削減が可能です。局所集塵は発生源近くで直接粉塵を吸引し、即時除去が可能で作業環境改善に役立ちます。
ある工場の事例では、アマノが個別集塵方式を提案し、クロスコンタミリスクの低減やダクト内風速の一定化を通じて、作業環境の改善と安全性向上を図っています。
ただし、集中集塵は設置費用が高額になりやすく、局所集塵は複数装置の管理が必要で、小型装置では処理能力に限界があります。どちらが適しているかは現場によって異なるため、集塵機メーカーへ相談しましょう。
目次
集中集塵と局所集塵の違い
大型集塵機などを用いた集塵システムは、工場や作業場で発生する粉塵や煙を除去し、作業環境の改善と作業者の健康を守るために重要な役割を果たします。集塵システムには大きく分けて集中集塵と局所集塵の2つの方式があり、それぞれ特性や適用範囲が異なります。
◇集中集塵とは
集中集塵とは、工場全体や広い作業エリアで発生する粉塵や煙を一つの集塵装置に集めて処理する方式です。集中集塵では、複数の作業ポイントから発生する粉塵をダクトで集め、中央の集塵機でまとめて処理します。
集中集塵システムの利点は、管理が一元化されているため、効率的なメンテナンスが可能であり、大規模な粉塵処理が必要な工場や作業場に適している点です。また、大規模な集塵機を使用することで、エネルギーコストの削減や設置スペースの節約にもつながります。
しかし、集中集塵には設置費用が高額になる場合や、ダクトの設置や配管工事が必要となるため、初期投資が大きくなるというデメリットもあります。また、システムが一つの集塵機に依存しているため、集塵機の故障時には全体の作業環境に影響が及ぶリスクが少なくありません。
◇局所集塵とは
局所集塵とは、特定の作業ポイントや機械の近くで発生する粉塵や煙を、その場で即座に除去する方式です。各作業ポイントに小型の集塵装置を設置し、発生源から直接粉塵を吸引するため、効率的に粉塵を除去できます。
局所集塵のメリットは、粉塵や煙の発生源近くでの即時除去が可能であるため、作業環境の改善効果が高いことです。また、個別に集塵装置を設置するため、システム全体の柔軟性が高く、変更や増設が容易です。
局所集塵のデメリットとしては、複数の集塵装置を管理する必要があるため、メンテナンスの手間が増えることや、各装置に対する個別の電力供給や設置スペースが必要となることが挙げられます。
また、小型の集塵装置では処理能力に限界があるため、大量の粉塵が発生する場合には対応が難しくなる可能性が高いです。
集中集塵を採用した顧客の課題

ある工場ではすでに集塵機を導入していたのですが、2つの課題が解決できていませんでした。
◇クロスコンタミ
クロスコンタミ(交叉汚染)は、異なる工程で生じる物質が混ざり合って発生する汚染のことです。特に、同一のラインで複数の製品を加工する場合や、同一の機器を使用して異なる製品を加工する際に発生します。
クロスコンタミにより、製品の品質が大幅に低下し、特に医薬品や食品など高い純度が求められる業界では重大な不具合です。例えば、製品の色や味が変わる、成分が混ざってしまうなどの問題がおこり、製品の再加工や廃棄、さらには顧客からのクレーム対応に追われます。
◇ダクト内の堆積
集中集塵システムでは、ダクトを通じて粉塵や煙を中央の集塵機に送りますが、ダクト内に粉塵が堆積することが問題です。
ダクト内の堆積が増えると、排気効率が低下し、システム全体の性能が悪化します。
さらに、堆積物が原因で火災や爆発が発生するリスクも高まります。
ダクト内に付着した粉塵が長期間蓄積されると、空気の流れが阻害され、排気不良が生じ、集塵機の効果が減少し、工場内の粉塵濃度が上昇していきます。
また、粉塵は可燃性のものが多いため、ダクト内に溜まった粉塵が何らかの原因で引火すると、火災や爆発を引き起こします。
局所集塵を採用した顧客の課題
局所集塵は作業環境の改善や従業員の健康保護に有効な設備ですが、導入にはさまざまな課題が伴います。これらの課題を正しく理解し、適切な対策を講じることで、局所集塵の効果を最大限に引き出せるでしょう。
◇設置スペースと導入コスト
局所集塵機は作業環境に応じた柔軟な設計が可能ですが、設置スペースの確保が課題となることがあります。特に、既存の工場や生産ラインに後付けする場合、十分なスペースを確保できず、機器の配置変更や追加工事が必要になることが少なくありません。
また、局所集塵機の導入には、本体の設備費に加えて、設置や配管、電源工事などの費用が発生します。このため、中小規模の工場では初期投資の負担が大きくなることがあります。さらに、適切な換気システムとの連携や、粉塵の種類に合わせたフィルター選定が求められるため、総合的なコスト管理が重要です。
◇ メンテナンス負担と運用コストの増加
粉塵や煙を効率的に吸引して作業環境を改善できる一方で、定期的なメンテナンスが必要です。特に、頻繁に稼働する現場では、フィルターの目詰まりや吸引力の低下が起こりやすく、清掃や交換作業の負担が増える可能性があります。
また、フィルターの交換頻度が増えると、それに伴い消耗品のコストや交換作業によるダウンタイムが発生し、運用コストが増加する要因となります。さらに、適切なメンテナンスを怠ると集塵機の性能が低下し、作業環境が悪化したり、設備全体の寿命が短くなるリスクもあるため、定期的な点検や予防保全の計画的な実施が重要です。
集塵機の選び方
集塵機を選ぶ際には、使用環境や吸引対象に適したモデルを選ぶことが重要です。粉塵や煙、液体の有無、作業の頻度などによって、適したタイプや機能が異なります。また、電動工具との連動機能やタンク容量、接続方式なども考慮するポイントです。適切な集塵機を選ぶことで、作業効率を向上させるだけでなく、作業環境の快適性や機器の耐久性も向上します。
◇用途に適した集塵機のタイプを選ぶ
集塵機を選ぶ際には、使用する環境や吸引対象を明確にすることが重要です。例えば、部材加工業では石膏ボードや断熱ボードの切削時に大量の粉塵が発生し、視界を遮るだけでなく、作業者の健康被害や機械の故障リスクも高まります。一方、金属切削工業では、加工中に発生する油煙ミストが作業環境を悪化させる原因となります。このように、現場の特性に合わせた集塵機の選定が不可欠です。
集塵機のタイプは大きく「乾湿タイプ」と「乾式タイプ」に分かれ、それぞれ特徴があります。乾湿タイプは、乾燥した粉塵に加え水や泥などの液体も吸引できるため、油煙や湿気を含む現場や水回りの清掃に適しています。乾式タイプは、乾燥した粉塵のみを吸引し、木屑や金属粉などの除去に適しています。
また、乾式タイプはホースが長めで電動工具との接続がしやすく設計されています。ただし、乾湿タイプはフィルターの目が粗く、細かい粉塵がフィルターを通過しモーターに影響を与える可能性があるため、液体を吸う必要がなければ乾式タイプの方がモーター保護の観点から適しています。使用環境や吸引対象を考慮し、最適なタイプを選ぶことで作業効率の向上や機器の長寿命化が実現できます。
◇電動工具との連動機能を考慮
電動工具と連動する集塵機を選ぶと、工具のスイッチをONにすると自動的に集塵機も作動し、作業中に発生した粉塵を即座に吸い取ることができます。これにより作業効率が向上し、清掃の手間も削減されます。特にDIYや木工加工を行う方にとっては、「連動付き」の集塵機が便利です。
一方、電動工具と接続しない場合は「連動なし」のモデルを選ぶことでコストを抑えられます。電動工具との連動方法には「コンセント接続」と「Bluetooth接続」の2種類があります。従来のコンセント接続は、連動コンセントの範囲内であれば機種を問わず使用でき、コスト面でも優れていますが、有線接続のため取り回しが制限される点がデメリットです。
一方、Bluetooth対応モデルは無線で連動できるため、作業スペースがスッキリし、取り回しが向上します。ただし、価格が高く、メーカーごとにBluetoothの仕様が異なるため、対応機種を事前に確認する必要があります。すでに特定メーカーの電動工具を使用している場合は、対応する連動方式をチェックし、最適な集塵機を選ぶことをおすすめします。
◇集塵機の容量を決める
容量が大きいほど多くのゴミを集められるため、ゴミ捨ての頻度を減らしたい場合は大容量モデルが適しています。特に、「頻繁にゴミを捨てるのが面倒」「長時間の作業で効率的に使用したい」という方には、大型モデルを選ぶと良いでしょう。ただし、タンクが大きくなると本体の重量も増えるため、取り回しや移動のしやすさも考慮する必要があります。
また、乾湿両用タイプの場合、「集塵容量」と「吸水量」が異なるため、注意が必要です。水や液体を吸う予定がある場合は、吸水量を確認しましょう。容量選びでは、作業環境や用途に合わせたバランスが重要です。作業スペースが限られている場合や持ち運びが多いならコンパクトなモデルを、長時間作業や大量の粉塵を処理するなら大容量モデルを選ぶと快適に使用できます。
アマノは個別集塵方式を提案
アマノは、工場や作業場の環境改善と効率化を目指し、個別集塵方式を提案しています。
個別集塵方式により、従来の集中集塵システムに伴う問題を解消し、より効果的な粉塵管理を実現することが可能です。
◇大幅にレイアウトを変更
アマノの提案する個別集塵方式では、加工機1台につき集塵機1台を設置することで、各加工機から発生する粉塵を即座に除去します。加工機から発生する粉塵を即座に除去することで、集中集塵方式で問題となるクロスコンタミのリスクの低減が可能です。
加工機のレイアウト変更により、異なる製品が同一空間で加工されることを避け、粉塵の混入を最小限に抑えることで、製品の品質が向上し、再加工や廃棄のコスト削減にもつながります。
◇ダクト内の風速を一定化
この工場ではダクト内の風速が不均一で、粉塵がダクト内に堆積しやすくなっており、排気不良や火災のリスクが高まっていました。
個別集塵方式にしたことで適切なダクト内搬送速度を維持しやすくなり、ダクト内の風速を一定に保てるようになりました。適切なダクト内搬送速度によって粉塵がダクト内に滞留せず、効率的に集塵機まで運ばれます。
作業環境の改善へ貢献
アマノは、作業環境の改善に向けてさまざまな対策の実施により多くの工場や作業場の効率化と安全性向上に貢献しています。
◇空調効率の向上
作業環境の改善において、空調効率の向上は重要な要素の一つです。アマノは、屋外排気が可能な集塵機を追加することで、空調効率の向上を実現しました。
従来のシステムでは、粉塵やオイルミストが空調機に入り込み、効率低下や故障のリスクが高まる問題があり空調機のメンテナンス頻度が増え、コストやダウンタイムが発生していました。
新たに導入した集塵機は、作業場内の粉塵やオイルミストを効率的に集め、屋外に排気することで空調機への負担を軽減することで、空調機のフィルターが詰まりにくくなり、空調効率が向上します。
作業場内の温度管理が容易になり、快適な作業環境が整い、空調機の故障リスクの減少による、メンテナンスコストの削減が可能です。
◇加工機の増設にも対応が可能
作業場の効率化を図る上で、加工機の増設は生産能力向上に不可欠です。アマノは、加工機1台につき集塵機1台を設置する個別集塵方式を採用し、加工機を別の加工室に移動させることで、スペースを有効活用しています。
レイアウト変更により、新たな加工機を追加する際のスペース確保と配線のしやすさが向上し、生産ラインの柔軟性が高まり、将来的な加工機の増設にも迅速な対応が可能です。
おすすめ集塵機メーカーを紹介
ここまではアマノの集塵機について紹介してきましたが、集塵機を扱うメーカーは他にも多く存在し、それぞれに強みや特徴があります。作業環境や用途に適した製品を選ぶことで、集塵効率の向上や作業環境の改善につながります。
◇アコー
アコーは、完全受注生産と自社一貫生産を強みとする集塵機メーカーです。千葉、静岡、大阪の3拠点に営業所を構え、経験豊富な技術スタッフが顧客の要望を直接聞き取り、最適な設計を提案しています。
静岡県磐田市の自社工場では、一枚の鉄板から製品を作り上げるこだわりの生産体制を整えています。環境対策や火災防止、風量の安定性など、既製品では対応できない課題にもフルオーダーで対応し、短納期での提供ができることが大きな特長です。
◇流機エンジニアリング
流機エンジニアリングは、独自の流体・環境制御技術を活かした環境ソリューションメーカーです。特に集塵機の開発では、省スペース設計やメンテナンスフリーを実現する高度なフィルター技術を強みとしています。
同社の独自の払落し技術を搭載したフィルターは、自動再生機能により目詰まりを防ぎ、安定した集塵性能を提供します。さらに、HEPAレベルのろ材を採用し、クラス100~10000の清浄度を達成する高性能モデルもあります。また、換気技術に精通した経験豊富な担当者が最適なソリューションを提案し、レンタル製品を活用したデモンストレーションにも対応しています。
◇デュコル
デュコルは、作業環境の改善に特化した集塵設備の専門メーカーです。集塵設備は、粉塵の発生源をできるだけ囲い込むことで風量を抑え、設備規模を最適化してイニシャルコストを削減することができます。
さらに、省エネ設計により消費電力や維持管理費を抑え、ランニングコストの低減を実現できます。作業環境の改善は、従業員の安全性や生産効率の向上に直結し、単なる付帯設備ではなく、企業全体の競争力強化に繋がる重要な要素です。デュコルは最小限のコストで最大限のパフォーマンスを発揮する提案力を強みとしており、企業の生産環境の最適化に貢献しています。
集中集塵システムは、工場や広範囲の作業エリアから発生する粉塵や煙を一箇所の集塵装置で処理する方式で、一元管理による効率的なメンテナンスと大規模な粉塵処理のニーズに応えます。このシステムはエネルギーコストの削減やスペースの節約が可能です。
一方、局所集塵では各作業ポイントに小型の集塵装置を配置し、効率的に粉塵を管理します。局所集塵の利点は、発生源近くで粉塵を速やかに除去できることで、作業環境の即時改善が可能となります。
ある工場の事例では、アマノの個別集塵方式を採用し、集中集塵システムの問題点を解消しつつ、より効果的な粉塵管理を実現しました。
この方式では、各加工機に一台の集塵機を設置し、発生した粉塵を即座に処理することで、クロスコンタミリスクを減少させ、ダクト内の風速を一定に保つことが可能です。これにより、粉塵のダクト内堆積を防ぎ、排気効率と安全性を向上させています。