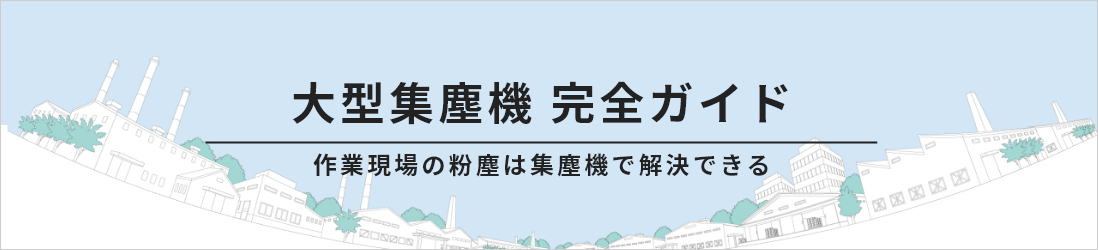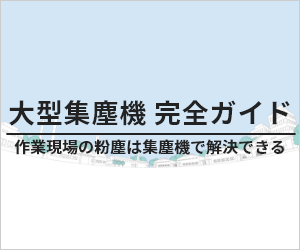大気汚染防止法は、日本の大気環境保護と国民の健康保護を目的に1968年に制定され、その後何度も改正を重ねています。法律は、工場や車両からの汚染物質排出を規制し、硫黄酸化物や窒素酸化物などの基準を定めています。
2021年の改正では、新たな建材の規制と作業基準遵守義務の拡大が主な内容で、特定工事や解体工事にも新たな義務が課せられました。企業や事業者はこれらの規制を正確に理解し、届出や対策を適切に行う必要があります。
大気汚染防止法の遵守は、都道府県ごとに異なる上乗せ排出基準を含め、厳格な審査と制裁が伴います。
目次
大気汚染防止法とは

大気汚染防止法は、多くの規制や対策を通じて、日本の大気環境の改善と国民の健康保護を目指しています。以下では、大気汚染防止法の概要と2021年の改正内容を解説します。
◇大気汚染防止法とは
大気汚染防止法は、大気汚染から国民の健康を守り、生活環境を保全するために1968年に制定された法律です。以来、何度も改正が行われています。この法律の目的は、工場や車両などから排出される汚染物質を規制し、大気の質を保つことです。
この法律では、硫黄酸化物、窒素酸化物、揮発性有機化合物、浮遊粒子状物質などの汚染物質に対する排出基準が設定されています。
事業者はこれらの基準を守ることが義務付けられており、汚染物質の排出状況を定期的に測定し、報告しなければなりません。違反した事業者には罰金や事業停止命令などの罰則が科されることもあります。
◇2021年4月に改正
大気汚染防止法の昨今の改正としては、2021年4月になされたものが挙げられます。これは解体工事による石綿(アスベスト)飛散の防止を目的に行われました。
主な改正内容として挙げられるのが、規制対象の拡大と作業基準遵守義務者の拡大です。規制対象の拡大では、これまでの建材に加え、石綿含有成形板等(レベル3建材)を含む新たな建材が規制対象となり、作業計画が義務化されました。
作業基準遵守義務者の拡大では、従来は元請業者のみが対象となっていた作業基準遵守義務が、2021年4月1日以降は下請負人にも拡大されました。
ほかにも、特定工事の元請業者に対する作業報告の義務化、一定規模以上の解体工事を実施する元請業者や自主施工者に対する事前調査報告の義務化などが盛り込まれています。
◇大気汚染防止法の歴史
明治時代に富国強兵や殖産興業が叫ばれて以来、日本は数々の公害問題を抱えてきました。それは高度経済成長期も変わらず、1961年には四大公害病の一つに数えられる「四日市ぜんそく」が発生しています。
こうした公害問題を抑制するため、国は1962年に「ばい煙の排出の規制に関する法律(ばい煙規制法)」を制定しました。しかし、この法律はばい煙以外の硫黄酸化物や窒素酸化物などへの規制に乏しかったため、大気汚染の根本的な改善には至りませんでした。
そうした事情を背景に制定されたのが、1968年の大気汚染防止法です。
先ほども触れた通り、大気汚染防止法は時代と共に改正を重ねており、1976年までに8回の排出基準の強化、1970年にカドミウム等5物質・上乗せ排出基準の追加、1974年に総量規制の追加がなされました。
企業が遵守すべきは大気汚染防止法だけじゃない?

企業や事業者は、大気汚染防止法の規制対象を正確に理解し、適切な対策を講じなければなりません。ここからは、大気汚染防止法の主な規制対象と上乗せ排出基準について解説します。
◇大気汚染防止法の規制対象は多岐に渡る
大気汚染防止法の規制対象は非常に広範囲に渡ります。以下では、ばい煙、粉じん、揮発性有機化合物など、主な規制対象について解説します。
・ばい煙
ばい煙とは、工場や発電所などの燃焼装置から排出される煙やすすのことです。これには、硫黄酸化物や窒素酸化物などが含まれ、発生源となる工場や施設に対して厳しい規制を行っています。
ばい煙には、施設ごとに国が定める一般排出基準の他、特別排出基準・上乗せ排出基準・総量規制基準が定められています。
・粉じん
粉じんとは、空気中に浮遊した粒子状の物質のことです。工場での作業や建設工事などで発生する粉じんは、呼吸器系の病気を引き起こす可能性があります。
中でも石綿は特定粉じんに指定されており、工場や事業所との境界における大気中の濃度上限、解体・改造・補修時の作業基準が定められています。特に境界における大気中の濃度上限を超えた場合、工場や事業者は都道府県知事の命令に従って業務の改善、施設の一時停止を行わなければなりません。
その他、石綿以外の一般粉じんについても、施設ごとに構造・使用・管理の基準が設けられています。
・揮発性有機化合物(VOC)
揮発性有機化合物とは、石油製品や化学製品から放出される有機化合物で、大気中で反応して光化学オキシダントやスモッグの原因となります。
一定規模以上の施設は揮発性有機化合物排出施設とされ、揮発性有機化合物の排出・飛散の抑制に関する自主的な取り組みが求められます。また、揮発性有機化合物の濃度に応じて定められた、施設ごとの上限値を守らなければなりません。
・特定物質
特定物質とは、物の合成や分解、その他の化学処理により発生する、健康・環境に悪影響を与えうる物質のことであり、アンモニアや一酸化炭素、メタノール、フッ化水素など28種類が指定されています。
施設の故障・破損時に発生する可能性が高いと見込まれているため、復旧や都道府県知事への通報など、事故対応が規定されています。
・有害大気汚染物質
有害大気汚染物質とは、低濃度でも長期的な摂取にリスクがある物質であり、ばい煙と石綿を除いた全248種類が指定されています。中でもリスクが大きいと考えられる23種類が優先取組物質、さらに早急な排出・飛散防止が求められる3種類が指定物質に指定されています。
有害大気汚染物質を排出する事業者は、排出を抑制すると共に、排出状況の把握に努めなければなりません。
・自動車排出ガス
自動車排出ガスとは、自動車や原動機付自転車が排出する物質であり、一酸化炭素や窒素酸化物、炭化水素、鉛化合物、窒素酸化物、粒子状物質などが指定されています。
メーカーに対する規制の他、低公害車の普及や公共交通機関の促進、自動車の利用の効率化などが盛り込まれています。
・水銀など
大気汚染防止法の一部改正により、水銀などが規制対象に追加されました。
水銀などを排出する施設は、種類や規模に応じた上限値を守らなければなりません。
◇上乗せ排出基準にも注意
ばい煙に対する基準には、国が施設ごとに定める一般排出基準の他、特別排出基準・上乗せ排出基準・総量規制基準があります。
特別排出基準とは、大気汚染が深刻な地域に新たな施設を増やすときの排出基準、上乗せ排出基準とは、社会的・環境的な条件を加味して都道府県ごとに定めたより厳しい排出基準です。また、総量規制基準とは、既出の排出基準でも規制が不十分な大型施設に対する、硫黄酸化物・窒素酸化物の排出基準です。
これらの基準は、特に汚染が深刻な地域で適用され、上乗せ排出基準に違反した場合、法的な制裁が科されることがあります。
対象施設は届出が必要

大気汚染防止法の対象となる施設を設置・使用・変更などの際には、事前の届出が必要です。事業者は規定に従い、適切に手続きを進めることが求められます。
◇対象施設
以下の施設に該当する場合は、届出が必要です。
・ばい煙発生施設
ガス発生炉や加熱炉、ボイラー、ばい焼炉、焼結炉、溶解炉、反応炉、直火炉、乾燥炉、電気炉などが含まれ、燃焼能力や原料処理能力、部位の面積など、それぞれ規定された条件を満たすもののみが該当します。
・粉じん発生施設
石綿を取り扱う特定粉じん発生施設、その他の一般粉じん発生施設に分かれます。
特定粉じん発生施設には、解綿用機械や混合機、紡織用機械などが含まれ、規定された原動機の定格出力条件を満たすもののみが該当します。ただし、湿式・密閉式のものは該当しません。
一般粉じん発生施設には、ベルトコンベアや堆積場、コークス炉などが含まれ、原動機の定格出力やベルト巾、バケットの内容積など、それぞれ規定された条件を満たすもののみが該当します。
・揮発性有機化合物排出施設
接着用や印刷用の乾燥施設、吹付塗装施設、工業製品洗浄施設などが含まれ、送風機の送風能力や洗浄剤が空気に接する面積、容量など、それぞれ規定された条件を満たすもののみが該当します。
・水銀排出施設
水銀を排出する施設の中でも、水俣条約に基づき規制を要するものを指します。具体的には、銅・金の一次精錬施設、石炭ボイラー、廃棄物焼却炉などが該当し、燃焼能力や原料処理能力、部位の面積など、それぞれ規定された条件を満たすもののみが該当します。
◇届出の種類と期限
届出には主に以下のような種類があり、それぞれ提出期限が異なります。
・設置
施設の設置を計画している事業者は、一般粉じん発生施設は建設開始前、それ以外は建設開始の60日前までに届出を行わなければなりません。この届出は、事前に行政側に対して計画内容を知らせ、法的基準を満たしているかどうかの確認を受けるために必要です。
・使用
大気汚染防止法の改正により新しく対象となった施設を保有する事業者は、対象となった日から30日以内に届出を行わなければなりません。昨今では、水銀排出施設が新しく対象となった例がありました。
・構造などの変更
施設の構造や設備、使用・処理方法を変更する事業者は、一般粉じん発生施設は建設開始前、それ以外は建設開始の60日前までに届出を行わなければなりません。具体的な事例としては、バーナーや煙突などの取り替え、施設の休止などが該当します。
・承継・廃止・氏名などの変更
施設の廃止・承継を行う事業者、施設の氏名や名称、住所、所在地を変更する事業者は、該当の日から30日以内に届出を行わなければなりません。
大型集塵機で大気汚染防止法を遵守

大気汚染防止法を守るために使用される大型集塵機にはさまざまな種類があります。以下では、大型集塵機の主な種類と特徴を解説します。
◇バグフィルター
繊維性のフィルターを通して空気をろ過し、粉じんを捕集する装置です。空気中の微粒子がフィルターに捕捉され、清浄な空気が排出されます。定期的なフィルター交換が必要ですが、高い捕集効率を持っています。
◇サイクロン
遠心力を利用して粉じんを分離する装置です。気流を旋回させることで、重い粉じん粒子を外側に押し出し、壁面に沿って落下させます。メンテナンスが比較的容易で、高温や高湿度の環境でも使用できますが、微細な粒子の捕集効率は低いです。
◇スクラバー
液体を使って空気中の粉じんやガスを洗浄する装置です。気体が液体と接触することで、汚染物質が液体に溶解または捕捉されます。ガス状の汚染物質の除去にも効果的ですが、液体の排水処理が必要となります。
◇電気集塵機
高電圧をかけて粉じん粒子に電荷を与え、集塵板に引き寄せて捕集する装置です。非常に高い捕集効率を持ち、微細な粒子にも対応できます。初期投資は高めですが、ランニングコストは最も低く、保守性も高いのが特長です。
おすすめの集塵機メーカーを紹介
こちらでは、大型集塵機を探している担当者の方におすすめのメーカーを3社紹介します。
◇株式会社アコー

アコー株式会社は、完全受注・自社一貫生産により、ニーズに合わせてカスタマイズした集塵機を提供しています。無駄のないシンプルな構造ゆえに、故障しにくくメンテナンスがしやすく、初期費用もランニングコストもお値打ちに抑えられます。
| 会社名 | 株式会社アコー |
| 本社 | <所在地> 〒279-0022 千葉県浦安市今川1-1-40 <電話番号> 047-352-4761 |
| 大阪営業所 | <所在地> 〒564-0062 大阪府吹田市垂水町3-24-1 <電話番号> 06-6368-9551 |
| 静岡営業所 | <所在地> 〒438-0211 静岡県磐田市東平松500-1 <電話番号> 0538-86-6478 |
| 公式ホームページ | https://www.acokk.co.jp/ |
また、環境に配慮した製品とサービスを提供し、持続可能な社会の実現を目指しています。最新の技術を駆使し、効率的で安全な集塵システムを提供し続けています。
株式会社アコーについて詳しく知りたい方はこちらも併せてご覧ください。
さらに詳しい情報は公式ホームページでも確認できます。ぜひチェックしてみてください。
◇アマノ株式会社
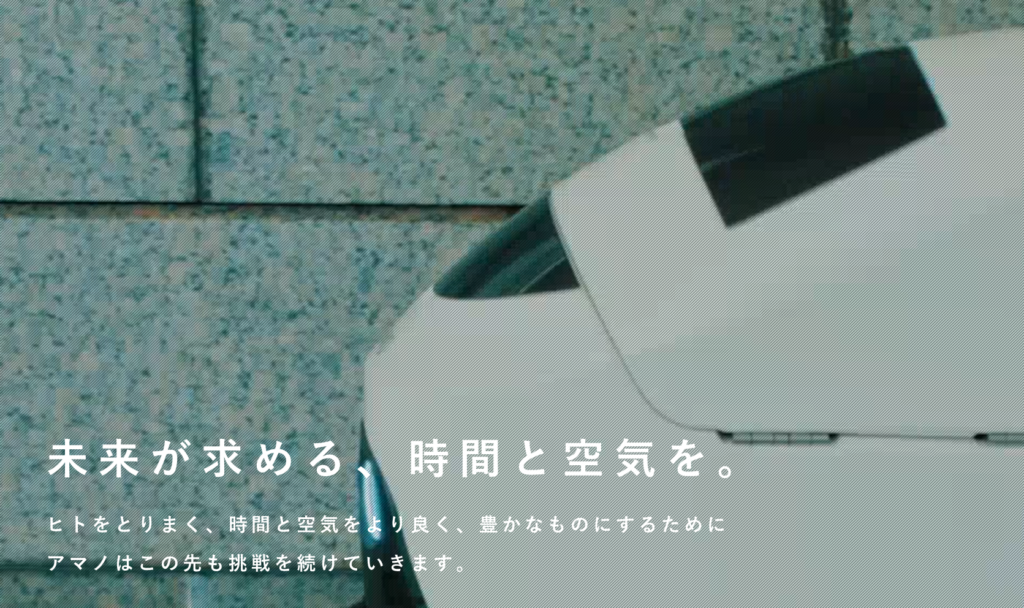
アマノ株式会社は「顧客第一主義」を掲げ、集塵機の約半分をセミオーダーで製造しています。設計からアフターフォローまで自社で一貫して行っており、特にアフターフォローの充実度には定評があります。
| 会社名 | アマノ株式会社 |
| 所在地 | 〒222-8558 神奈川県横浜市港北区大豆戸町275 |
| 電話番号 | 045-401-1441 |
| 公式ホームページ | https://www.amano.co.jp/ |
また、地域社会に根差した製造・販売体制を整え、顧客の要望に即した製品の創造・開発に取り組んでいます。持続可能な社会の実現を目指し、環境に配慮した製品とサービスを提供しています。
アマノ株式会社について詳しく知りたい方はこちらも併せてご覧ください。
◇リョウセイ株式会社

ジェットパルス式集塵機を中心に、様々な集塵機を手掛けてきたメーカーであり、幅広いニーズに対応できる産業用バックフィルターが強みです。集塵機の選定から設置まで自社で一貫して行っており、カスタマイズや特殊仕様にも対応しています。
| 会社名 | リョウセイ株式会社 |
| 所在地 | 〒463-0048 名古屋市守山区小幡南2-6-8 |
| 電話番号 | 052-794-3211 |
| 公式ホームページ | http://www.ryousei.com/ |
また、環境保全にも配慮し、ISO14001認証を取得しています。地域社会に根差した製造・販売体制を整え、持続可能な社会の実現を目指しています。
真空企業株式会社について詳しく知りたい方はこちらも併せてご覧ください。
大気汚染防止法は、日本の大気環境保護と国民の健康保護を目的に1968年に制定されました。以来、工場や車両からの汚染物質排出を規制し、硫黄酸化物、窒素酸化物、揮発性有機化合物などの排出基準を定め、大気の質を保つための枠組みを提供しています。
2021年の改正では、特に建材の規制と作業基準遵守義務の拡大が注目されました。新たにレベル3建材(石綿含有成形板など)が規制対象に加わり、事業者はこれらの材料を使用する際には作業計画の届出が必要です。また、解体工事や特定工事においても、事前調査報告の義務が課されました。
企業や事業者にとって、大気汚染防止法の遵守は法的な義務だけでなく、社会的責任も含みます。地域ごとに異なる上乗せ排出基準にも対応し、厳格な審査と罰則を避けるためには、正確で適切な届出と対策が不可欠です。この法律の適用範囲は広く、ばい煙や粉じん、揮発性有機化合物など、多岐にわたります。
特に粉じん発生施設の設置では、集じん機の選定や運用方法など具体的な計画が求められます。大気汚染防止法を遵守するための技術的な解決策として、バグフィルターやサイクロン、電気集塵機などの大型集塵機が使用され、それぞれの特性に応じた効率的な粒子捕集が行われています。