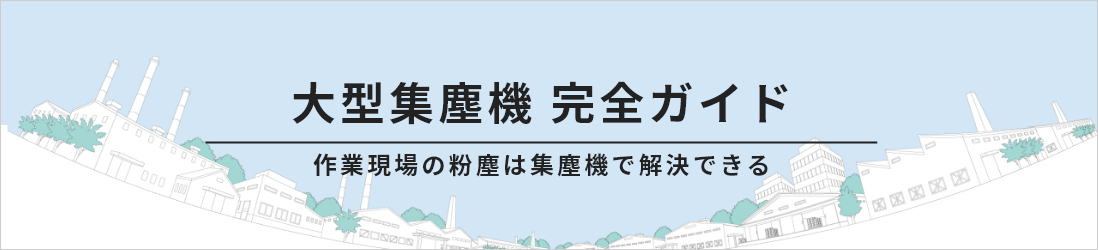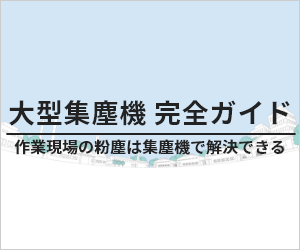集塵機は、チリやホコリだけでなく、木、金属、石膏、液体など様々な種類の物質を吸い取ることができますが、機種によってはうまく捕集できなかったり、故障を招いたりする可能性もあります。そのため、集塵機を購入する際は、使用する物質の種類や量、状態に応じて、適切な集塵機を選ぶことが重要です。今回は、集塵機の選び方が分からない方のために、主な集塵機の種類とそれぞれの特長について詳しく解説していきます。
目次
集塵機とは?

引用元:photo AC
集塵機は、工場や作業現場で発生する粉塵を効率的に吸引し、除去するための重要な機械です。掃除機のような形状をしていますが、通常の掃除機とは異なり、細かい粉塵や有害物質を安全に取り除くことを目的としています。解体作業や切断作業、研削作業など、粉塵が大量に発生する現場で特に重要な役割を果たしています。集塵機を導入することで、粉塵による健康リスクや火災、爆発の危険を軽減でき、作業者の安全を守るとともに、作業効率の向上にも繋がるでしょう。また、集塵機は設置場所や使用目的に応じて、さまざまなタイプやサイズが選べるため、幅広い業界で活用されています。
掃除機と集塵機の違いについて
掃除機と集塵機は、どちらも粉塵やゴミを吸引する機械ですが、その目的や仕組みには大きな違いがあります。掃除機は主に家庭やオフィスで使われ、床に落ちたホコリやゴミを吸い取るのに適しています。一方、集塵機は工場や作業現場などで発生する大量の粉塵を効率よく吸引し、空気中の微細なゴミまで除去できるのが特徴です。それぞれの特性を理解し、適切な場面で活用することが重要です。
掃除機
掃除機は、狭い吸引口から空気を一気に吸い込むことで強い負圧を生み出し、床に溜まった埃やゴミを効率的に取り除く仕組みになっています。床面に密着させて使用することを前提としているため、カーペットの奥に入り込んだゴミを吸い取るのは得意ですが、空気中に浮遊する粉塵の捕集には向いていません。また、掃除機のフィルターは比較的小さく、細かい粉塵を大量に吸い込むと目詰まりを起こしやすい構造です。フィルターが詰まったまま使用を続けると吸引力が低下し、最悪の場合モーターの焼き付きなど故障につながる可能性があります。そのため、掃除機は一般的な家庭清掃には適していますが、工場や作業現場の粉塵処理には十分な性能を発揮できません。
集塵機
集塵機は、掃除機と比べて吸引圧力はそれほど高くありませんが、その分、風量を大きくすることで一度に大量の粉塵を吸い込むことが可能です。特に、切削や研磨作業などで発生し、空中に舞い上がった粉塵も効率的に吸引できるため、作業環境の衛生管理に大きく貢献します。
また、集塵機には複数のフィルターが搭載されており、フィルターの面積も広いため、細かい粉塵を効果的に捕集できます。目詰まりしにくく、長時間にわたって安定した吸引力を維持できるのも特徴です。
さらに、使用するダクトホースの直径も大きく異なります。掃除機では一般的にφ38~φ50程度のホースが使われますが、集塵機ではφ75以上、大型のものではφ500にもなる機種があり、用途に応じて効率的に粉塵を集められます。
集塵機の種類は大きく分けて4種類

引用元:photo AC
集塵機の選び方が分からない方は、まずは集塵機にどのような種類があるか理解しておくことが大切です。集塵機は大きく4つの種類に分類できます。それぞれの特長は、次のとおりです。
バグフィルター
ろ過式集塵機のことで、フィルターで粉塵を捕集します。集塵能力を維持するために、フィルターに付着した粉塵は、定期的に逆洗(パルスジェット)で払い落とされます。フィルターの種類には、ポリエステル、耐熱ナイロン、ガラス繊維などがあり、用途に合わせて選べます。サイクロン集塵機では難しい細かい粉塵でも、99%捕集でき、幅広い風量にも対応可能です。
ウェットスクラバー
水に落とし込み粉塵を捕集するため、火災の心配がなく、油煙混じりの粉塵、爆発性の高い粉塵などに適しています。フィルターを使った集塵機よりもサイズがコンパクトなため、設置しやすいのもメリットです。
サイクロン集塵機
遠心力を使って粉塵を分離し捕集します。フィルターが不要なため、メンテナンスが楽でランニングコストも安いです。粉体のみならず、水、油、金属などに使用できます。
電気集塵機
電気集塵機は電気モーターを使用してファンを回転させ、空気中の微粒子に電荷を付加することで集塵します。各種加工工場や建設現場などにおける廃棄物や粉塵の収集に適しています。省エネタイプが多く、運転コストを抑えられるのがメリットです。
ポイント1・乾湿両用か乾式専用か
集塵機には、乾湿両用タイプと乾式専用タイプがあります。このふたつの違いは吸い込むものの違いで、選び方を誤ると故障の原因になります。乾湿両用タイプと乾式専用タイプの違いも、事前にチェックしておきましょう。
乾湿両用タイプ
フィルターを変えることで、乾燥した粉塵と液体の両方を吸い込めますが、機種によってはフィルターの交換が不要なものもあります。ただし、乾湿両用のフィルターは目が荒く、細かい粉塵がモーターまで届いて故障する可能性があるため、細かい粉塵には向きません。また、ホースの長さは、乾式専用タイプのホースと比較して短く、約2mです。
乾式専用タイプ
乾燥した粉塵専用の集塵機です。液体には対応していないため、液体を吸い込むと故障を招くので注意が必要です。乾式専用タイプは、フィルターの目が細かく、細かい粉塵を捕集することができるため、液体を吸う必要がない場合には、乾式専用タイプの購入をおすすめします。また、ホースの長さは約5mあります。
粉塵と液体の両方を吸える乾湿両用タイプのほうが性能が高いように見えますが、細かい粉塵を捕集する場合には、乾式専用タイプが適しています。
ポイント2・電気工具と接続するか
集塵機は、電動ノコギリやグラインダーなどと接続して連動させて作業することも可能です。電動ノコギリと集塵機を接続する場合、電動ノコギリを作動させると自動的に集塵機も作動します。おが屑やゴミはすぐに吸い取られ、掃除をする必要がなくなるため、作業効率がアップします。電動工具を接続する場合は、以下のポイントをチェックしてください。
連動機能が搭載されているか
電動工具は、乾湿両用タイプ、乾式専用タイプのどちらにも接続できます。ただし、すべての機種に電動工具を接続できるわけではなく、接続し連動させられるのは、連動機能が搭載された集塵機のみです。連動機能付きかどうかは、製品のスペックに記載されています。
T型ノズルが付いているか
電動工具と接続して使用するだけあれば特に問題はありませんが、掃除機としても使う場合は、T型ノズルが必要です。連動機能が搭載された集塵機には、T型ノズルは別売りになることが多いので、購入する際に付属されているか、オプションか確認が必要です。
ポイント3・吸引する物質で選ぶ
集塵機を選ぶ際には、吸引する物質の種類を考慮しましょう。吸引する物質には、乾いた粉塵、水分を含んだ粉塵、さらには液体そのものなどがあり、それぞれに適した集塵機を選ばないと十分な性能を発揮できません。特に乾湿両用のモデルと乾式専用のモデルではフィルターの構造が異なり、誤った使い方をすると故障の原因にもなります。
乾いた粉塵
乾いた粉塵を吸引する場合、基本的にどの種類の集塵機でも対応できます。特に、乾式専用の集塵機は、細かい粉塵を効率よく捕集できるように設計されており、石膏ボードやコンクリート、サイディング、米ぬかなどの粉塵処理に適しています。乾式専用の集塵機は、フィルターの目が非常に細かく、微粒子を逃さずにキャッチできるため、作業環境の清潔さを保つのに最適です。しかし、乾式専用の集塵機は水分を含む粉塵や液体の吸引には対応しておらず、誤って水分を吸い込むとフィルターが目詰まりを起こし、故障の原因となることがあるため、使用環境に注意が必要です。
水分を含んだ粉塵
作業現場によっては、水分を含んだ粉塵を吸引する必要がある場合があります。例えば、湿ったコンクリート粉塵や金属加工時に発生する湿った切り粉などが該当します。このような場合には、乾湿両用の集塵機を選びましょう。乾湿両用の集塵機は、水分を含んだ粉塵をスムーズに吸引できるように設計されており、フィルターの目が比較的粗く作られています。ただし、フィルターの目が粗い分、細かい粉塵を長時間吸引すると目詰まりを起こしやすくなるため、定期的なメンテナンスやフィルターの交換が重要になります。また、吸引する粉塵の性質によっては、モーターに負担がかかることがあるため、使用する際はメーカーの推奨する用途を確認することが大切です。
水分や液体
液体や大量の水分を吸引する場合は、乾湿両用の集塵機の中でも特に液体対応のモデルを選ぶ必要があります。こうした集塵機は、フィルターに加えてタンク構造が工夫されており、水分や液体を効率よく回収できる設計になっています。例えば、作業現場でこぼれた冷却水や、食品加工現場で発生する液体汚れなどを処理する場合に役立つでしょう。乾湿両用の集塵機であっても、水分の多い環境での使用を想定していないモデルもあるため、購入前に液体の吸引が可能かどうかをしっかり確認することが重要です。また、水分を多く扱う現場では、吸引後の排水処理のしやすさや、フィルターの耐久性、清掃のしやすさも考慮することで、より快適に使用できます。
ポイント4・集塵容量はどれくらいか
集塵機の容量とは、タンクの容量のことです。タンクの容量が大きければ、それだけ多くの粉塵を捕集できるので、集めた粉塵を頻繁に捨てる必要がなく、長時間作業ができます。しかし、その一方でサイズが大きくなり、移動や収納が難しくなりますので、作業頻度や収納場所を考慮して選ぶことが重要です。
基本的な容量のサイズは8Lと15Lのふたつです。必要があれば、もっと大きいサイズを探すことも可能です。一般的なサイズで、容量の違いでサイズにどれぐらいの違いが生じるかというと、HiKOKIが販売している製品の場合、以下のとおりです。
容量 製品名 本体寸法(幅×奥行×高さ)
8L RP80YB(L) 331×364×361mm
15L RP150YB(L) 331×364×418mm
容量は約2倍違いますが、本体寸法の幅と奥行きは同じで、高さが57mm高くなっているだけです。数センチの違いであれば容量が大きいほうが便利ですが、メーカーによってサイズは異なり、数センチでも違いでも収納場所に収納できないこともあります。容量で選ぶときは、必ず本体寸法もご確認ください。
集塵機には、バグフィルター、ウェットスクラバー、サイクロン集塵機、オイルミスト集塵機の4種類があり、液体が吸える乾湿両用タイプと液体が吸えない乾式専用タイプが存在します。選ぶ際には、用途に合わせた選択が重要であり、また、容量を選ぶ際には本体寸法も確認する必要があります。
種類が多くて選べない場合は、メーカーに直接問い合わせて、用途に応じた適切な機種を紹介してもらうとよいでしょう。よろしかったら以下に参考になる3社紹介を紹介します。
◇株式会社アコー

株式会社アコーは、1977年に創業された集塵機専門メーカーで、パルスジェットバグフィルタやウエットスクラバー、マルチサイクロン集塵機などを製造・販売しています。高性能な製品を提供し、作業環境の改善に貢献することを目指しています。顧客一人ひとりの要望に応じたオーダーメイド集塵機を提案し、最適なソリューションを提供しています。
| 会社名 | 株式会社アコー |
| 本社 | <所在地> 〒279-0022 千葉県浦安市今川1-1-40 <電話番号> 047-352-4761 |
| 大阪営業所 | <所在地> 〒564-0062 大阪府吹田市垂水町3-24-1 <電話番号> 06-6368-9551 |
| 静岡営業所 | <所在地> 〒438-0211 静岡県磐田市東平松500-1 <電話番号> 0538-86-6478 |
| 公式ホームページ | https://www.acokk.co.jp/ |
また、環境に配慮した製品とサービスを提供し、持続可能な社会の実現を目指しています。最新の技術を駆使し、効率的で安全な集塵システムを提供し続けています。
株式会社アコーについて詳しく知りたい方はこちらも併せてご覧ください。
さらに詳しい情報は公式ホームページでも確認できます。ぜひチェックしてみてください。